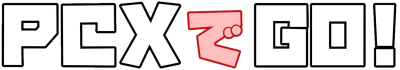一冊の本に巡り合い、私にはバイクが必要なのだと知った。
その後の行動は早かった。誰にも相談せず免許を取り、バイクを買った。
実家に住んでいたけど、誰にも相談せず、事後報告で済ました。
私はいつも両親に反抗していたので、報告しても返ってくる言葉は何も無かった。
ただ、暗くて悲し気な視線だけを感じてた。
そんな当時のことを振り返ってみよう。

著者プロフィール
名前:みどりのシカ
女性だけどバイクに魅せられた。20歳で初めて自転車に乗れるようになり、その2年後に中型二輪免許取得。きっかけは片岡義男「幸せは白いTシャツ」と三好礼子氏との出会い。
20代の頃、ほぼ毎日オートバイに乗っていました。遠くは四国、沖縄まで旅をしました。
わけあってオートバイを手放してから、かなりの年月が経過。また乗りたい気持ちを抱えてジタバタしています。
フウテンのトラ子

私は何者でも無い自分に苛立ち、周囲を傷つけてばかりいた。母とも必要最低限のコミュニケーションしか取っていなかった。
バイクを買ったことを事後報告した時、母は反応できないほど困惑していた。そして家にやって来たバイクを見て、うろたえていた。
けれど念願のバイクを手に入れた私は、走るのに夢中で心配する母の姿を気に留めなかった。
「ちょっと行ってくる」
それだけ言ってツーリングに出かけ、帰るのは夜中。
数日、帰らなかったりもした。
そんな日々が続いたある日、母は言った。
「フウテンのトラ子だね」
いつの頃からかヘルメットを持って家を出ようとする私に、母は大きなおむすびを1つ持たせるようになった。
「じゃまだからいらない、積むとこ無いし」
そう冷たく言い放つ私に、それでも母は無理やりおむすびを持たせるのだった。
バイクで走り疲れると、国道沿いの縁石に座り込んで休んだ。そしてウエストバッグの中でつぶれたおむすびを頬張った。
それは、とてもとても美味しくて、母に冷たい言葉を放った自分を顧みて涙が滲んでくるのだった。
胸の奥が痛んだけれど、私は自分のことで精一杯だった。
「修理できないの?いくらかかるの?」と母は言った

それから何年後かに、私は結婚を機に実家を離れた。
けれど、長くは続かなかった。
DVと経済的な困窮という結婚生活の末に離婚。
その後、2度の事故もあり経済的な事情からバイクを手放すしかなかった。
母に私は言った。
「バイク手放すことにした」
「そうだね、もういい年だし、危ないからやめたほうがいいね」
私はてっきり、母はこう言うと思っていた。
しかし、母はあまりにも意外なことをあっさりと言ったのだ。
「修理できないの?いくらかかるの?」
何と答えたのか記憶にない。
あまりにも意外なことを言われ、その言葉だけが頭の中で鳴り響いていた。
誰よりも私を理解していたのは、母だった。
バイクに乗ってる私は生き生きとしていた。そのことを誰よりも見ていたのは母だった。
「バイクって、気持ちいいんだろうな・・」と父は言った

父は元教師だった。
赤ちゃんから幼児の頃まで、私は溺愛されていたらしい。
だけど、ちょっと変わった娘を理解することは困難だったようだ。いつしか私は父への反感を募らせ、父とは口を利かなくなった。
神経質で頑固で病弱で、病院通いが絶えなかった父。
ある日、バイクを道に出そうとしている私の近くに父がいた。私は目も合わせず、もちろん無言だ。
そんな私に、父はポツリと言った。
「バイクって、気持ちいいんだろうな・・・」
私は内心うろたえた。何言ってんだこのオヤジ。
泣きそうになるのをこらえてバイクを道に押し出し、エンジンをかけた。
しばらく経ったある日、ヘルメットを持って部屋を出ると、トイレに入ろうとしていた父と一瞬だけ目が合った。もちろん、挨拶なんてしない。お互いに。
何も言わずに私はバイクに乗り込み、アクセル全開で国道4号線バイパスをひたすら南下した。
何故か、ふと東側の路地に曲がりたくなった。スピードを落として路地を進んでいくと、一本の煙突が見えた。
何か嫌な感じ。
何かを感じ、そこからUターンして家に帰ることにした。
帰宅するとバイクを降りる間もなく叔母が慌てた様子で駆け寄り、大声で言った。
「どこに行ってたの!お父さんが亡くなったんだよ」
最後に父に会ったのは私だった。
それから何週間か、罪悪感で泣き暮らした。
理解してなかったのは私だった

- 自分が何者か分からず、苛立っていた私
- 就職に失敗し、自分の居場所を見失った私
- 一冊の本から、バイクと出会い救われた私
- 結婚に失敗してしまった私
そんな私の傍らにいつも居てくれたのは両親だった。
いつも私を見守っていてくれた。
私のことを何も理解してないと思っていたけれど、理解してなかったのは私だった。
父にしても母にしても、自由に生きられない、そんな人生を生きていたのかもしれない。
私が自分らしく自由に生きようと藻掻くのを、我が事として見守ってくれてたのだ。
そう思えるようになったのは、つい最近のことだ。
併せて読みたい