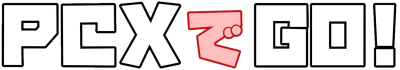私が21歳のとき、片岡義男の「幸せは白いTシャツ」と出会った。
1人の女性がバイク旅を通して自立していく物語だ。
この本を通して、私が私らしくあるにはバイクが必要なのだと知った。
今思い返せば、本を読んだ勢いのままバイクの世界に入ったのは、若さゆえの一途さであり、真っ暗な海に飛び込むような無謀な行動だった。
だけれど、あの日の私には紛れもなく確信があった。
きっとバイクは楽しいに違いない。
なぜなら私は知っていたからだ。
バイクで走ると、鼻で空気を切り裂くことになる。
すると空気は風となり頬からアゴを伝い、うなじに抜けて髪をたなびかせる。
同時に、体にまとわりつく邪気を吹き飛ばしてくれる。
その感覚を私は知っていた。
自転車で走ると風が気持ちいい。
きっとあの感覚と同じだ。
つい最近、風の感覚を知って感激したばかりだったから、直ぐに解った。
そう、私は20歳になって初めて自転車に乗れるようになったのだ。
それはあまりにも衝撃的で、感動的で、素晴らしい体験だった。
だから、確信があった。
バイクなら、自転車の何百万倍も心地よいに違いない。
せっかくだから
20歳で初めて自転車に乗れた時のことを、振り返っておこう。
あれは、私がまだ学生だった時のことだ。

著者プロフィール
名前:みどりのシカ
女性だけどバイクに魅せられた。20歳で初めて自転車に乗れるようになり、その2年後に中型二輪免許取得。きっかけは片岡義男「幸せは白いTシャツ」と三好礼子氏との出会い。
20代の頃、ほぼ毎日オートバイに乗っていました。遠くは四国、沖縄まで旅をしました。わけあってオートバイを手放してから、かなりの年月が経過。
けれど幸運なことに、いきなりバイク復帰しました。25年ぶりの相棒は、KAWASAKI 250TR。愛称をティーダと名付けました。ただいま、自分慣らし中です。
夏合宿と自転車と大きなアザと私

私は写真部だった。
しかし、最初から写真に興味があった訳では無い。
親友たちに「入部しよう!」と誘われたからついて行っただけだ。
流されるまま、写真部に入部した。
けれど、いつのまにかのめり込んでいた。
写真部の夏合宿
写真部には毎年夏に合宿があり、その年は岩手県の遠野へ行くことに決まった。
遠野での活動は、サイクリングで名所旧跡を巡りながら写真を撮るという内容だった。
え?あたし、自転車に乗れない・・・
私も子供の頃のある時期に、人並みに自転車の練習をした。
しかし練習で転んで脱臼した過去がある。
その時に立てた、『一生、自転車には乗らない』という誓いを守りつつ大人になった。
バイクを見た時も、『一生、バイクには乗らない』と誓った気もするがそれは別の話だ。
夏の合宿が決まってから、旅行雑誌や「遠野物語」(柳田國男)を読みふけった。そして、そこに描かれた素晴らしい風景の中を、自転車で走れたらどんなに素晴らしいか、どんなに気持ちがいいだろうかという想像がどんどん膨らんだのだ。
私は、自分の意志で何かを決めたり行動したりする性格ではなかった。流れに流されることが多かった。
写真部に入ったのも、その1つだ。
だけど、私は決意した。
自転車に乗ろう!
特訓と挫折

転んだらどうしよう、ぶつかったらどうしよう。
そんなマイナスの要因はほとんど考えなかった。
乗りたい、ただそのことだけが頭の中に溢れていた。
しかし
- 自分の自転車が無い
- 乗り方を知らない
一人では無理だ・・・。
思い余った私は、当時反抗して口もきかなかった両親に言った。
「あたし、自転車に乗るから。練習するから・・・」
その時の両親の呆れた顔は、今も鮮明に覚えている。写真に残さなかったのは後悔でしかない。
両親と共に、近くの空き地で自転車の練習が始まった。
『20代の女子、親に手伝ってもらって自転車を練習する』の図。
カッコ悪いったらない。
近寄りたくもない父に自転車の後ろを支えてもらい、数時間何度も練習した。
しかし、乗れなかった。
一生懸命手伝ってくれた両親に悪たれをついて、たった一日で私は練習を辞めた。
「もう、いい」
私はこみ上げる感情を押さえ、静かに言った。
たった1日の練習で乗れるはずが無い。
その通りだ。私も1日で乗れるとは思ってなかった。
何かしらのきざしが見い出せたなら、私も諦めはしなかった。
けれど、100万年練習してもムリだと、私は悟ったのだ。
遠野の風になる

そして、合宿当日。
みんな嬉々としてレンタル自転車を借りて乗っていく。
「わたし、乗れないから・・・いいや」
口では言いながら、押して歩けばいいよね、と一台の自転車を借りてみた。
友人たちに、乗れるの?大丈夫なの?と言われながら。
「ほら、乗れないよ~」とふざけて乗ってみせたら、乗れた。
嘘のような本当の話だ。ほんとに乗れた。誰かが後ろを持ってくれているとしか思えなかった。
なぜ、両親との練習ではきざしも見えなかったのに急に乗れたのか、今でも謎だ。
当時の私は神を信じていなかった。今も信じていないが理由が見つからない。
火事場の何とかなのか、本当の私は出来る子なのか、遠野という土地のおかげなのか。
いずれにしても、強く具体的に望めば、願いは叶うのだ。
風の心地よさを知った
田んぼのあぜに落ちたり、トンボが次々に顔にぶつかったり。
のろのろと、よろけながらだけど、確かに遠野の風景の中を自転車で走った。
風がとても気持ち良かった。
トンボが口に入りそうになるのもかまわず笑いながら、素晴らしい風景の中を夢中でこいだ。
楽しかった。今でも鮮明に記憶しているとびきりの体験だった。
こうして、私は風の心地よさを知った。
大きなアザと私

それからの私は、もう夢中で毎日自転車に乗った。
弟が持っていた青いサイクリング車を我が物にして、走り続けた。
- 看板にぶつかりもした
- 他人にブツかりそうにもなった
乗れるようになったばかりの危うさはあったが、走り続けた。
だんだんスピードを出せるようになった頃、手に掛けたビニール袋が前輪に絡まり、大転倒。
慣れた頃が一番危ないという、教訓どおりだった。
顔面を打撲、大きなアザができた。
それでも自転車にのることは止めなかった。
年をとったいま、あのアザの跡がシミとなって浮き出てきている。
このシミは自分で自由を手に入れた時の証、言うなれば勲章なのだ。
誇らしくもある。
バイクはもっと心地よいに違いない

自転車に乗れた2年後、私は教習所への坂を弟の青い自転車で上っていた。
急な長い坂を一度も足をつかずに登れるようになった頃、私は中型二輪免許を取得した。
もし風を切る心地よさを知って無かったら、バイクに乗ることはなかっただろう。
風の気持ち良さを教えてくれたのは自転車だった。
こういう前章があったからこそ、赤い背表紙の小説と出会ってバイクに乗ることの素晴らしさ、求める世界がそこにあることを具体的にイメージできたのだ。
そして、その予感が正しかったことを私は知ることになる。