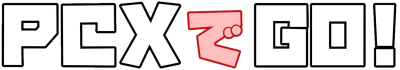離婚後、私は憧れの港町で一人暮らしを始めた。
そこは憧れていた通り、華やかで刺激的な街だった。
けれど、私の居場所では無かったようだ。
バイク乗りにとって、男か女か、若いか年取ってるか、そんなに重要な問題なんだろうか?
そんなことを問う機会が、何度もあった。
失礼、というよりは、無礼な出来事だ。
そして、私はバイクを降りた。

著者プロフィール
名前:みどりのシカ
女性だけどバイクに魅せられた。20歳で初めて自転車に乗れるようになり、その2年後に中型二輪免許取得。きっかけは片岡義男「幸せは白いTシャツ」と三好礼子氏との出会い。
20代の頃、ほぼ毎日オートバイに乗っていました。遠くは四国、沖縄まで旅をしました。わけあってオートバイを手放してから、かなりの年月が経過。
けれど幸運なことに、いきなりバイク復帰しました。25年ぶりの相棒は、KAWASAKI 250TR。愛称をティーダと名付けました。ただいま、自分慣らし中です。
バイクショップ近くの銭湯にて

一人暮らしを始めた土地で、お世話になることにしたバイクショップ。
その近くには、銭湯があった。
バイクをショップの前にとめ、その銭湯へ通うのが楽しみの1つだった。
あの日もバイクを置いて銭湯へ行った。
ガエルネオフロードブーツを靴箱の上に乗せ、暖簾をくぐって自販機でチケットを買う。
髪をかき乱しながら、女湯の暖簾に向かう。
すると、
「男湯はこちらですよ!」
受付のおばさんが、慌てて誘導する。
「え?あたし、女ですけどぉ・・・」
小声で言う私を無視して、おばさんはまた言った。
「男湯、あちらですよ!」
いつものこと、だけど

こんな勘違いはバイクで走っていると、あちこちであった。
身長も高く、肩幅も広く、化粧もなおざりだったから仕方がない。
もちろん、お洒落なんてまったくしていない。
いつだって、Tシャツに古びたジーパン。
そして、履き慣れたガエルネオフロードブーツが定番のスタイルだ。
こんな外見だから、男と間違われるのは慣れている。
笑顔を作って軽口を返し、笑い話に変えて、やり過ごすのがルーティーン。
でも内心は、深く傷ついている私がいた。
バイクショップのクラブミーティングにて

私がお世話になることにした港町のバイクショップは、かなり刺激的だった。
昼間からビールをあおる店主がいたり、いつ死んでもおかしくない走り屋的なバイク乗りがわんさといた。
どうも~と言って、簡単にお近づきになれるような輩たちではない。
特別なオーラをまとい、目つきが普通ではないし
同じ匂いのする者としか言葉を交わさない。
くたびれた街乗りオフローダーの私などには見向きもしない。
かと思えば、地味な大人しい青年がいつもショップで何をするでもなく、そこにいたりする。
彼はいつも笑顔で、フレンドリーに話しかけてくれた。しかし、存在感が薄く友達にはなれなかった。
ある日、店主の奥様に声をかけられた。
「ショップのバイククラブのミーティングに参加してみたら?」
クラブミーティング

私は誘いに乗り、私にとっては高額な参加費を払った。
そしてミーティング当日の早朝、会場の箱根へ向かった。
その日は朝から生憎の雨だったが、箱根に着くころには雨は上がっていた。
天候などお構いなしで、ミーティング会場には既に多くのバイクの群れ。
漫画の世界から抜け出してきたような、革ジャンに同じチーム名を背負ったオートバイ乗りたち。
大勢が、ミーティング会場の広場にたむろっていた。
うわ~。やばいとこ来たかも・・・
特に仲のいい仲間もおらず、浮いた存在の私には居場所は無かった。
海へ
仕方なく、喧騒を離れて近くの岩場で一人海水に浸かり、身体を冷やすことにした。
朝の雨と気温の高さで湿度が異常なほど高く、汗と排ガスにまみれた体が不快だったからだ。
しばらくぼんやりと海水に浸かっていると、存在感の無い青年がなにか言いに来たが、適当に返事をした。
海から出ると、バンダナで軽く水滴をぬぐい、水着の上にTシャツとジーパンを身に付けた。
塩水で濡れたままの頭をヘルメットにねじ込んで、同じく湿ったままの足に靴下を履きガエルネに押し込む。
バイクで走れば、その内に乾くだろう。
誰に挨拶するでもなく駐車場へ向かった。
磯と汗の生臭い香りを漂わせ、私は何も食べず、飲まず、会場を後にした。
彼女は、オートバイを降りた

しばらくして、私はオートバイを手放した。
なぜ、あれほどのめり込んでいたものを、あっさりと手放してしまったのか。
そうでは無い。あっさりでは、無かった。
いろんなことが重なって、降りるしかなかった。
最後まで、そのバイクショップには馴染めないままだった。
もし、そのバイクショップに馴染めていたなら、
走り屋の伴侶ができたか
自分が走り屋になって
大好きな港町を毎晩徘徊していたかもしれないね。
思い出深い、刺激的な港町での出来事だ。
併せて読みたい